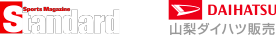小学生として最後の大会で6年生が全力を出し切る
2月25日、甲府市小瀬スポーツ公園体育館で行われた「ダイハツプレゼンツ 第2回トライアングルチャンピオンシップ」。大会には山梨、静岡、長野の3県から昨年の「ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会」の県予選を含む県大会でベスト8に入った小学4、5、6年生に出場資格が与えられ、山梨県からは46人(男女各23人)が出場した。
開会式では、大会スポンサーを代表して山梨ダイハツの中島健二社長が挨拶。「この大会は、小学生のバドミントンレベルの向上を目指し、各県の小学生バトミントン連盟様と弊社グループのコラボレーションで2020年2月に第1回を開催しました。21年、22年の2年間はコロナ感染防止の観点から中止とせざるをえず、大変悔しい思いをしました。皆さまには試合ができることを大いに楽しんで、思う存分に力を発揮していきましょう」と選手にエールを送った。

3年ぶりに開かれた大会で、挨拶をする山梨ダイハツ・中島社長
6年生男子では、昨年5月の全国ABC県予選で3位になった伊藤恵太に注目が集まった。伊藤は予選リーグ初戦序盤、相手に左右に振られながらもついていき、チャンスでスマッシュを決めるなど健闘を見せた。しかし、テクニックで勝る相手に徐々にリードを広げられ第1セットを落としてします。続く第2セットも流れがつかめず敗れた伊藤は、続く2試合目も黒星となり、3位トーナメントへ進むことに。この悔しさを晴らしたい伊藤は、初戦で相手を圧倒すると勢いに乗り、準決勝、決勝でも鋭いスマッシュと粘り強いレシーブを武器に、いずれもストレート勝ちを収めて、3位トーナメントを制した。
一方の6年女子は、全国ABCに出場した津金心奏が欠場となり、県予選2位の秋山音花に期待となった。秋山は、予選リーグを1勝1敗で終え、2位トーナメントへ。初戦は力強いスマッシュで勝利したものの、準決勝では第3セットまでもつれ、最後に力尽きた。

3位トーナメントでは実力を発揮してみせた伊藤

秋山は粘り強いプレーを見せたが、悔しい結果に終わった
昨年県代表武田が5年生男子で表彰台に立つ!
5年男子には、昨年の全国ABCにA級男子代表として出場した武田琉依が出場。武田は危なげない試合運びで予選2試合を勝利して、決勝トーナメントへ進出を果たす。トーナメント初戦は、稲田結心(長野)選手と対戦。第1セットを落とした武田は、第2セット、「自分のモチベーション。自分がもっと動けるように声を出しています」と自分のプレースタイルを思い出し、得点を決めるごとに声を出して流れを引き寄せる。そしてこのセットを奪うと、第3セットも強烈なスマッシュで相手に付け入る隙を与えず勝利した。
決勝進出をかけて山田源(静岡)と激突した準決勝では、序盤から相手にペースを握られ、ストレートで敗退。それでも気持ちを切り替えて挑んだ3位決定戦では、第1、第2セットともに相手に11点差をつける大勝でメダル獲得につなげた。また、武田と同じ勝沼ジュニアバドミントンスポーツ少年団に所属し、県予選2位だった内田心堂も得意のクロスカットを武器に決勝トーナメントに進出するも初戦で敗れ悔しさをにじませた。
一方の5年女子には、全国ABC県予選3位だった望月絆愛が3位トーナメントを制した。

雄叫びを上げて喜びを表現した武田

予選リーグでは悔しさが残ったが5年生女子3位トーナメントを制してみせた望月
4年生の3位トーナメント決勝で山梨県勢が激突
4年生男子では、3位トーナメント決勝で江口成那と依田樹の山梨県勢対決が実現。試合は、大会前の課題であった横からのショットに磨きをかけた依田が、第1セットを21対3で圧勝。続く第2セットも依田がペースを握り、江口は粘り強いショットで反撃を試みるが流れは変わらず。終わってみれば21対11で依田が勝利を収めた。
一方の女子は、昨年の全国ABC女子B級で代表の座を争った坂本絢音と中村夏海が3位トーナメント決勝で激突。「追い込まれる場面もあったが、粘って頑張れました」と振り返った坂本が、県代表の経験を存分に発揮して、勝利した。

父親から独特と表現されるプレースタイルで4年生男子3位トーナメントを制した依田

実力を発揮して4年生女子3位トーナメントで優勝した坂本
全試合終了後には閉会式が行われ、各部門3位までに入った選手に賞状とメダルが授与された。また、各部門の優勝者には日本代表としても活躍する奥原希望と桃田賢斗のサイン色紙も贈呈された。

優勝者に贈られたサイン色紙がこちら

各部門の決勝トーナメントの上位3人には表彰状とメダルが贈られた
大会終了後、5年男子で3位に輝いた武田は「準決勝で負けたことは悔しかった。次の試合ではもっと早く動くことができるようになりたい」とコメント。6年男子3位トーナメント優勝の伊藤は「静岡県、長野県の選手たちと試合ができる機会は滅多に無いので、良い経験になりました」と大会を振り返った。
また4年女子3位トーナメント優勝の坂本は「今日だけではなく、今後の練習で悪かったプレーを全部直していきたい」と改善点を口にし、5年女子3位トーナメント優勝の望月は「自分の思い通りのプレーができなくて、攻められるのが続いてしまったけど勝てて良かったです」と涙ながらに答えてくれた。
山梨県勢が頂点に立つことはできなかったが、出場選手全員が今ある力を存分に発揮するプレーを見せてくれたことは間違いない。今大会で得た経験を、次なるステップへの大きな糧として、さらなる成長へとつなげてもらいたい。
文・元木風羽 撮影・加藤誠夫